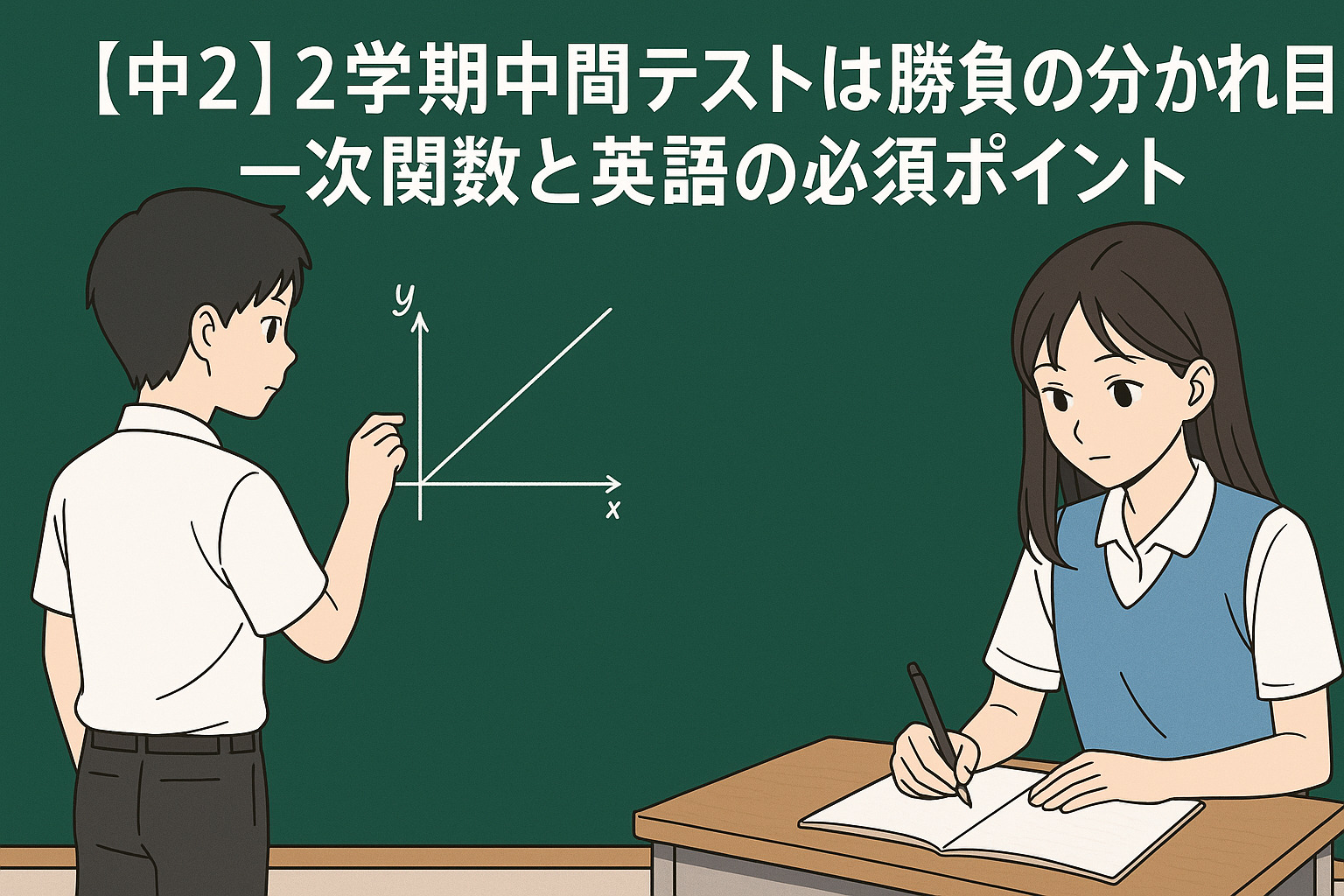中学2年生のみなさん、そして保護者の皆さま。
11月の「2学期中間テスト」は、まさに勝負の分かれ目となるテストです。
2学期の内容は、どの教科も一気にレベルが上がります。
特に数学の一次関数と英語の文法(have to・must・動名詞など)は、ここでしっかり理解できるかどうかで、今後の成績が大きく変わっていきます。
■ 数学:一次関数を制する者は中2を制す!
2学期の数学の中心単元は、なんといっても一次関数。
ここを曖昧にしたままだと、3年生の「二次関数」そして、高校受験の得点にまで影響してしまいます。
特に定期テストでは、「動点の問題」が頻出。
グラフの折れ曲がる点(折れ目の座標)をしっかり把握し、
それぞれの部分で式を立てて「代入→代入→整理」していくのがポイントです。
たとえば、A点からB点、B点からC点へと点が動くような問題では、
動いている範囲と時間をしっかり区別して考えることが大切。
「どの範囲でどんな式が成り立つのか」を頭の中で整理できるようにしておきましょう。
hal学習塾では、グラフの書き方・式の立て方・表の使い方など、
一人ひとりの理解度に合わせて丁寧に解説します。
「なんとなくわかった」ではなく、「自分で説明できる」レベルまで引き上げる指導を徹底しています。
■ 英語:have to、must、動名詞、疑問詞+to不定詞を攻略せよ!
2学期の英語は、内容も文法も一気に難しくなります。
今回のテスト範囲として予想されるのは――
- have to + 動詞の原形(〜しなければならない)
- must + 動詞の原形(〜しなければならない)
- 動名詞(〜すること)
- 疑問詞 + to + 動詞の原形(何をすべきか、どこへ行くべきか、など)
これらはどれも、「文の中で名詞のように使う」という共通点があります。
文法を丸暗記するよりも、「どんな働きをしているか」を理解しておくことが重要です。
また、学校によっては前回のテスト範囲の「接続詞(because, if)」も範囲に入る場合があります。
英語は「文章の構造を理解できるかどうか」が勝負。
テストでは「文法の穴埋め」だけでなく、「読解問題」「英作文」でも差がつく単元です。
hal学習塾では、文法の理解→練習→実践の3ステップで、
「使える英語力」に変えていく授業を行っています。
ただの暗記ではなく、「自分の言葉で文を作れる」レベルを目指しましょう。
■ 2学期中間テストは“伸びる生徒”と“止まる生徒”の分岐点
中2の2学期は、部活でも責任が増し、学校生活も忙しくなる時期。
しかし、この時期に学習習慣を崩さないことが、後の受験勉強を左右します。
1学期である程度点数が取れていた生徒も、2学期で一気に差が開くのはこの時期。
「ちょっと油断したら平均点以下」というのもよくある話です。
逆に、ここで基礎を固めた生徒は、2年生後半、そして受験学年に入ってから一気に伸びます。
焦らず、目の前の一問一問に丁寧に向き合うことが何より大切です。
■ hal学習塾からのメッセージ
一次関数も英語の文法も、「わかる」と「できる」はまったく別物です。
テスト本番で点を取れるようにするには、
「解き方の再現練習」と「自分で説明できる力」を身につけること。
hal学習塾では、その「できるまでの過程」に徹底的にこだわります。
集団授業でありながら、ひとりひとりの理解のズレを見逃さない指導を行っています。