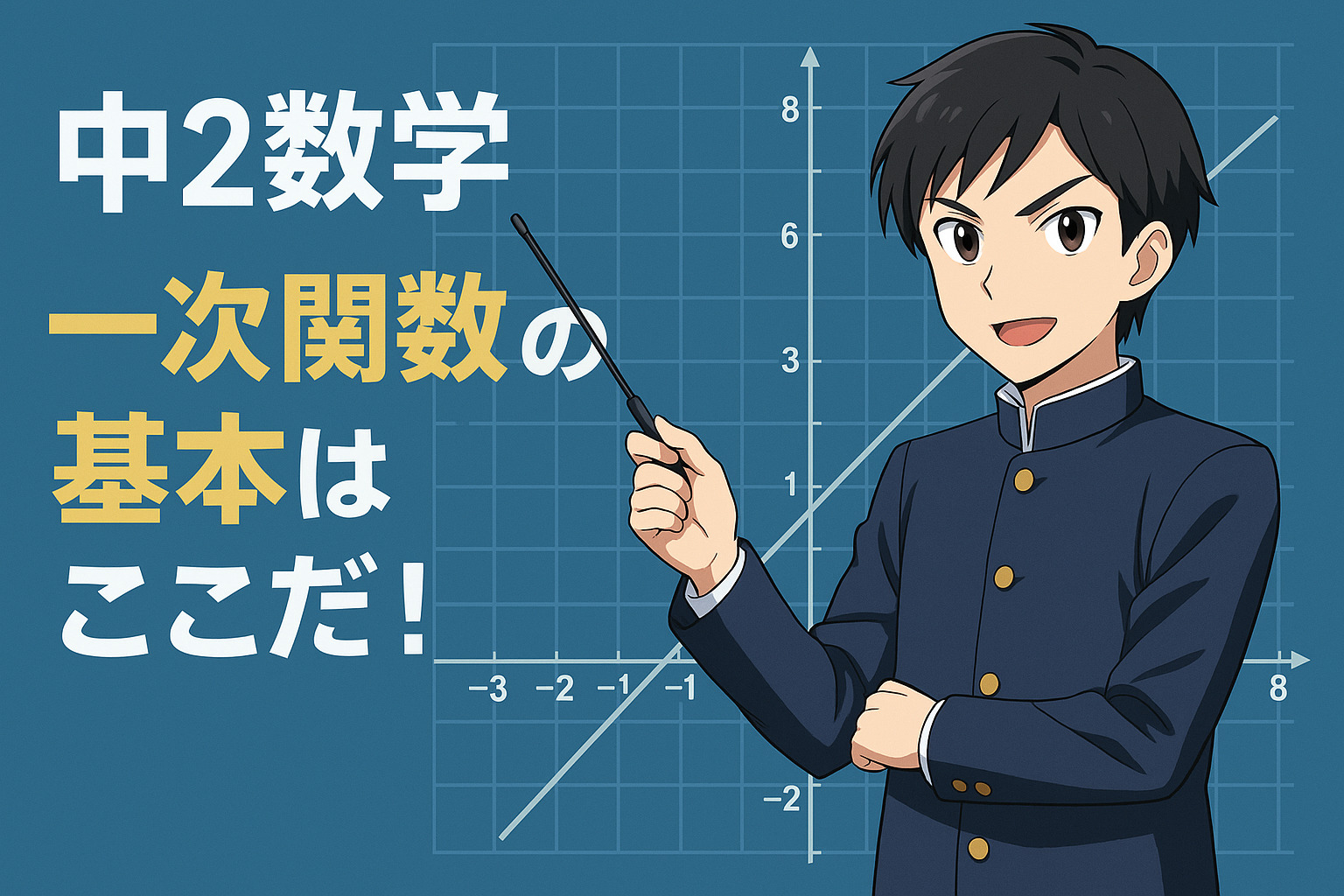中学2年生の1学期期末テスト。
数学の大きなヤマ場となる単元、それが 一次関数 です。
この単元は、ただ公式を暗記しているだけでは得点に結びつきません。
「変化の割合?傾き?切片?よく分からない…」という生徒も多いはず。
でも、ここでつまずくと、この先の数学全体に大きく響いてきます。
一次関数の基本は「見える化」!
一次関数の考え方は、とてもシンプルです。
たとえば、こんな式:
y = 2x + 3
この式を見て、あなたはどんなイメージが浮かびますか?
ただ「覚える」だけの勉強では、何も見えてきません。
でも、式の構造を 視覚的にイメージ できるようになれば、急に面白くなってきます。
覚えるべき3つのキーワード
テスト前に、まずはこの3つを正確に覚えましょう。
① 変化の割合
言いかえれば「1増えたとき、どれだけ増えるか?」
→ 計算方法: 変化の割合=yの増加量xの増加量変化の割合 = \frac{yの増加量}{xの増加量}変化の割合=xの増加量yの増加量
この「1あたりの増え方」を見抜く力は、文章題やグラフの問題で大活躍します。
② 傾き(aの部分)
式が y = ax + b の形になっていれば、aが傾きです。
「傾き」は、グラフがどれだけ急に上がっているか、または下がっているかを示す数値。
- a > 0 → 右上がり
- a < 0 → 右下がり
- a = 0 → 横一直線(定数関数)
③ 切片(bの部分)
y軸と交わる点、すなわち x=0 のときの yの値です。
式の「+3」や「−5」の部分がこれにあたります。
「頭の中でグラフを描けるか?」が勝負の分かれ目!
グラフの問題でよくあるミスは、「とりあえず表を作って、点を打って、なんとなく線を引く」というやり方。
それでは意味がありません。
ポイントは…
- 傾きがプラスかマイナスか
- 切片がどこか
- どの点を通るのか
- xとyの関係がどんな動きをするか
これらを 頭の中でイメージできること が、一番大事です。
hal学習塾ではこう教えています
hal学習塾の授業では、ただ解き方を教えるだけでは終わりません。
- グラフを「ストーリー」として理解する
- なぜそうなるのかを「言葉」で説明できるようにする
- 自分の手で式を作り、グラフを予想して、検証する
このプロセスを大切にしています。
定期テストは「パターン暗記」ではなく「意味理解」で差がつく!
一次関数の問題には、パターン化された出題も多くあります。
でも、どんなに問題集を繰り返しても、意味が分かっていなければ応用問題ではつまずいてしまいます。
逆に、意味を理解していれば、初見の問題でも戦える。
これが、本物の学力です。
テスト直前のチェックリスト ✅
- 「変化の割合」の計算方法は完璧?
- 傾きと切片を式から読み取れる?
- y = ax + b の式をグラフにできる?
- グラフから式を逆に作れる?
- 文章問題を読んで、関係を式にできる?
これらができていれば、一次関数はもう怖くない!
保護者の皆様へ
一次関数は、今後の中学数学だけでなく、高校数学や理科の内容にも関わってきます。
このタイミングで基礎が抜けてしまうと、将来的に大きな差となって表れます。
hal学習塾では、理解→定着→応用までしっかりサポートいたします。
「できるようになった!」という自信が、次の単元への前向きな姿勢にもつながります。