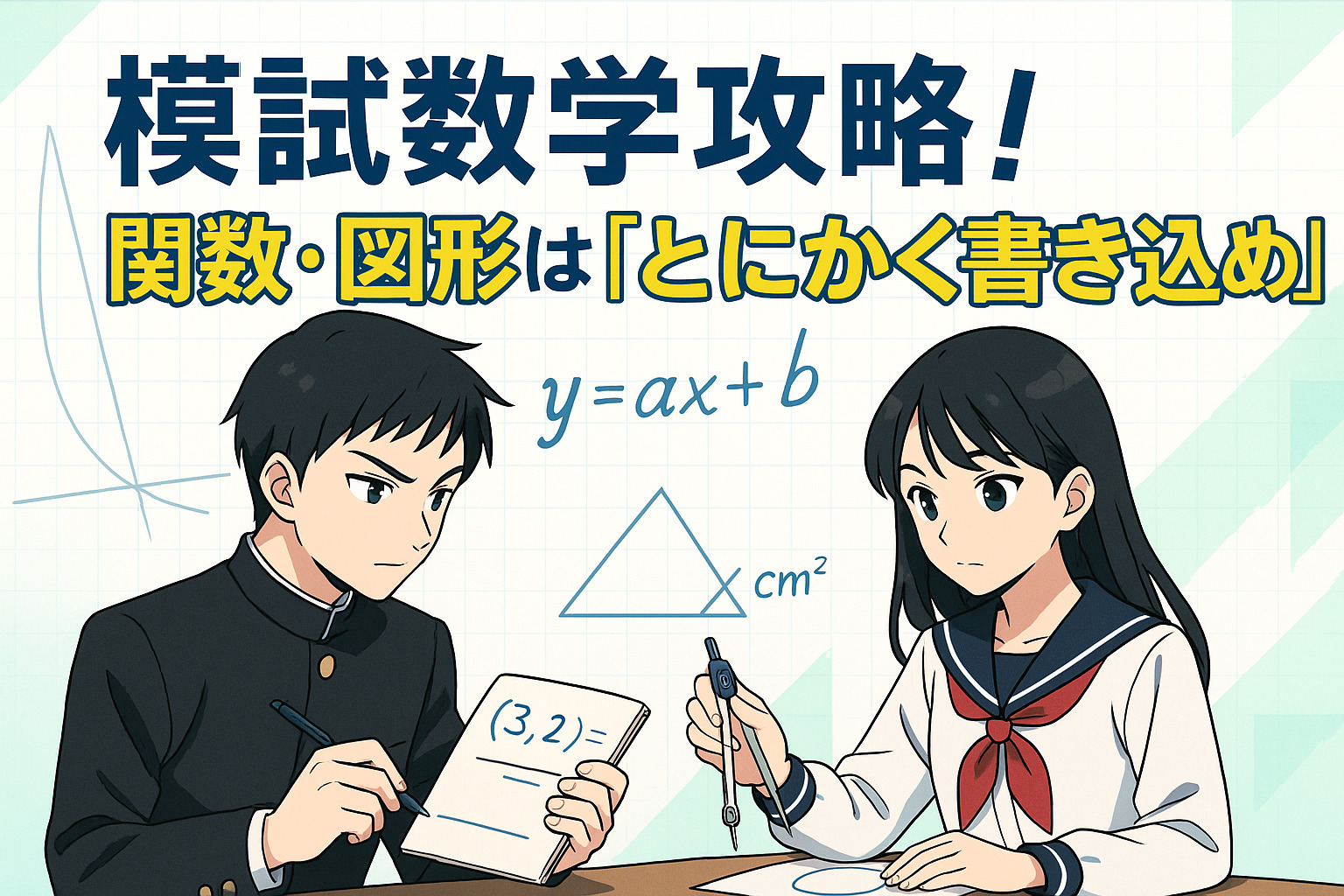「模試の数学、関数や図形の問題が時間内に解ききれない」
「解き方の糸口がつかめないまま、最後は勘で答えてしまう」
そんな悩みを抱える中学生は多いのではないでしょうか?
実は、模試の数学で点を取れる人と取れない人の差は、問題用紙の使い方にあります。
答えが書いてあるのは解答欄。でも、解けるかどうかは「途中の紙」にかかっているのです。
書き込むことで、頭が整理される
関数や図形の問題は、文章の中に重要な数字やヒントが隠れています。
座標、直線の式、線分の長さ、角度、面積…。
これらを頭の中だけで整理するのは無理です。プロでも無理です。
例えば、以下のような問題を想像してみてください。
点A(3,2)、点B(7,6)を通る直線の式を求めよ。
また、この直線とx軸との交点をCとする。△ABCの面積を求めよ。
このとき、何も書かずに頭の中で計算するのはほぼ不可能。
途中でどの数がどこから出てきたか、すぐに分からなくなります。
ところが、問題用紙や下書きに
- 座標を書き出す
- 求めた「傾き」や「切片」をメモする
- 図にCの座標を入れる
- 座標を使って辺の長さを計算するメモを書く
こういった「書き込み」をするだけで、手順が整理され、解くスピードも正確さも一気に上がるのです。
図形問題は「絵を描いて、長さや角度を書き込む」!
模試の図形問題は特に要注意です。
問題に印刷された図は、小さくて情報も少ないことがほとんど。
そこに、問題文に書かれた情報を自分で追記する作業が必須です。
例えば
- 与えられた長さを書き込む
- 角度を書き入れる
- 平行マーク、垂直マークを描き足す
- 求めた長さや比をメモする
こうした書き込みを怠ると、最初の条件すらすぐ忘れてしまい、何度も問題文を読み直す羽目になります。
それは大きな時間ロス。模試では時間との戦いです。
特に中学数学の「証明問題」では、書き込んだ図がそのまま答えに直結することも多いです。
書き込みこそ最強の武器だと思ってください。
模試本番でやってみよう
- 座標は問題文から見つけ次第、即座に図に書く
- 長さ、傾き、切片などは空いたところにメモする
- 小さくてもいいので図を自分で描き直す
- 直線の交点は座標を必ず書き入れる
- 証明のときは補助線もどんどん描く
書き込みが多いほど、問題を「自分のもの」にできます。
逆に、頭の中だけで解こうとするのは、模試で失点する人の典型的なパターン。
模試本番、鉛筆を置く手を止めないこと。
「書き込み」は、模試数学を制する最大のテクニックです!