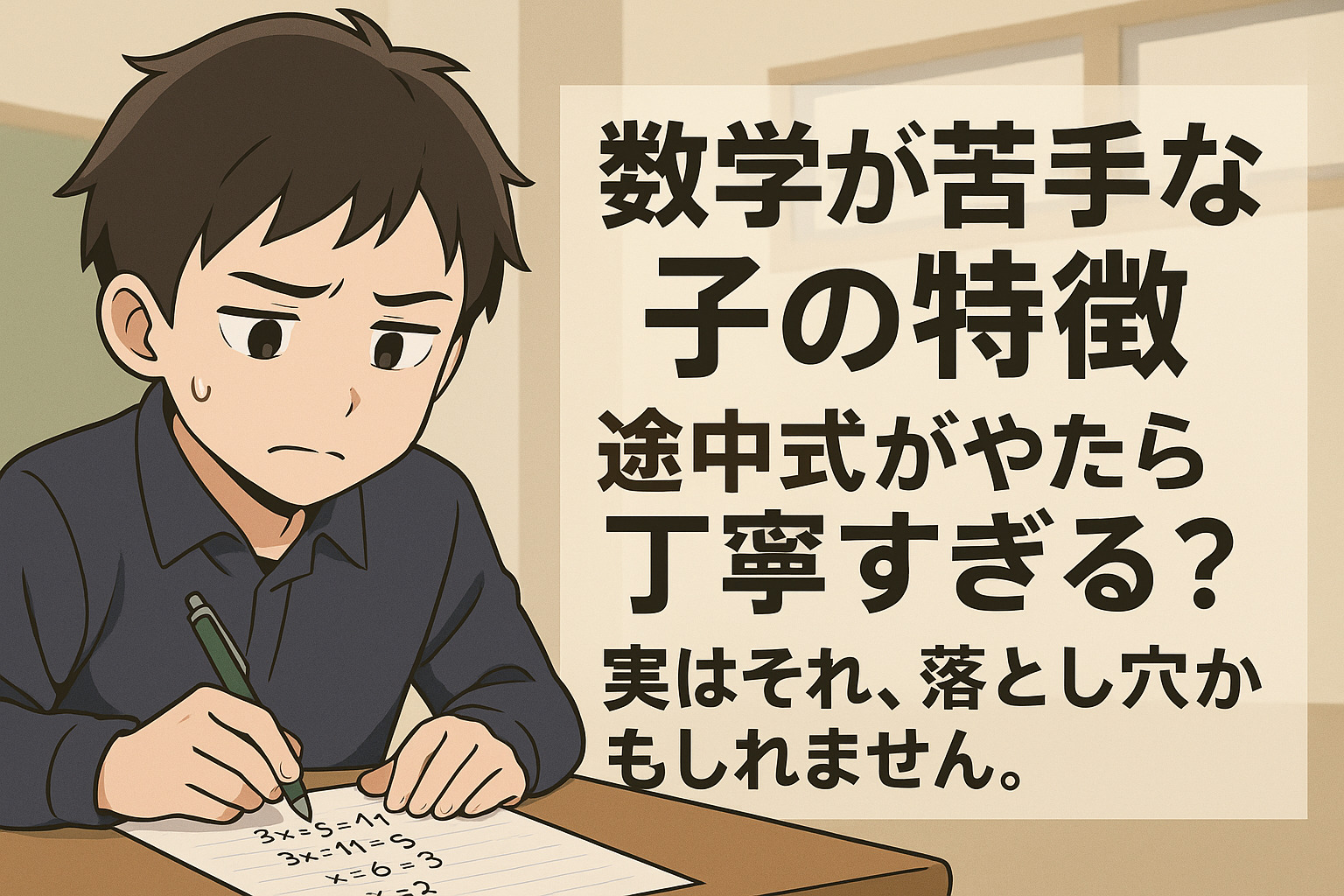中学生の数学を見ていると、ある傾向に気づきます。
それは、「途中式が異常に丁寧な子ほど、数学が苦手で点数が低いことが多い」ということ。
もちろん、丁寧に書くこと自体が悪いわけではありません。むしろ、「字が汚くて自分でも読めない」「どこで間違えたかわからない」といったミスを防ぐためにも、整った途中式は大切です。
でも、問題は——
「考えながら式を書いているのではなく、写経のように“決まりごと”として書いている」
このケースです。
「とりあえず書いとけばいいや」の途中式
たとえば、
3x+5=11
↓
3x=11−5
↓
3x=6
↓
x=6÷3
↓
x=2
こんな感じの途中式を、どんなに簡単な問題でも毎回これくらい丁寧に書く子がいます。
でも、よく見ると、本人はこの途中式を「読んで」いないんです。ただ「こうやって書くといいって言われたから」と思考を止めて、作業として書いている。
こうなると、途中式は「考えるためのツール」ではなく、「手を動かすだけのルーティン」に成り下がってしまう。
結果、問題の本質が見えなくなる→ミスが減らない→点数が上がらないという悪循環に…。
式を「考えるため」に使う
数学が得意な子は、必要なときだけ式をしっかり書き、頭で処理できるところはテンポよく進めていきます。
3x+5=11 なら「5をこっちに移して、6。x=2だな」と、頭の中でさっと見通しを立てる。
もちろん、頭の中だけで処理してミスが増えてしまうタイプには、途中式を丁寧に書かせることが必要です。
でも逆に、すべてを途中式に任せてしまって、思考を放棄している場合は要注意。
式はあくまで「頭の中を整理するための補助ツール」です。
「書けば安心」ではなく、「何を書いているか理解しているか」が大事。
式を書くスピードが遅い=思考のテンポが悪い?
やたら途中計算が丁寧すぎる子は、どうしても問題を解くペースが遅くなります。テストの時間配分にも悪影響が出やすいです。
1問1問に時間をかけすぎて、
「最後の問題にたどり着けなかった」
「計算問題で時間切れになった」
というパターン、経験ありませんか?
また、式を写すのにばかり集中して、
「計算ミスに気づけない」
「答えを見直す時間がない」
というのも、数学あるあるです。
解決のヒント:「考える→書く→確認する」のリズムを
数学の途中式は、「とりあえず書く」ではなく、「理解を深めるために書く」ことが大切。
そのためには、以下のようなリズムを意識してみましょう。
- まず、頭の中でざっくり全体像をつかむ
- 必要なところだけを式にする
- 途中で「本当に合ってるかな?」と確認しながら進む
つまり、
思考→記述→確認
このサイクルが回っている状態が理想です。
逆に、
記述→記述→記述(思考ゼロ)
では、どんなに丁寧に書いても、点数にはつながりません。
hal学習塾では、途中式の「目的」を教えます。
hal学習塾では、ただ「式を書こう」「ノートを丁寧に」と言うのではなく、
「なぜ式を書くのか」「何のためにノートに書くのか」という本質的な部分から伝えています。
ノートをチェックしながら、
・どこまで頭で考えていいか
・どのタイミングで式にすべきか
・計算を見える化する意義はどこにあるか
そんなことを日々、生徒たちと話し合いながら指導しています。
途中式が必要なタイミング、書かなくてよいタイミング、
それを見極められるようになると、
数学が「速く・正確に」解けるようになります。