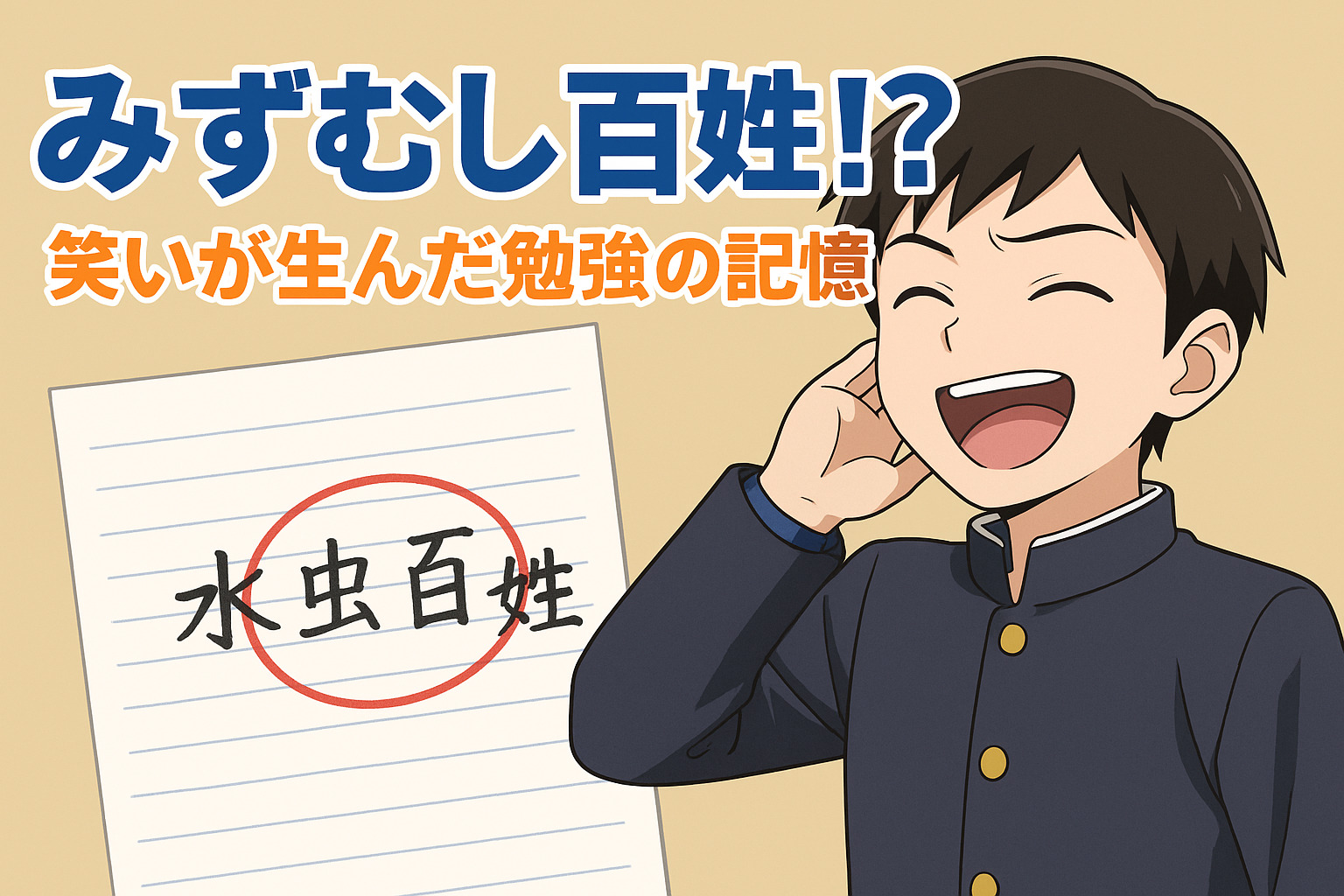中学2年生のテスト対策授業、社会の一コマ。江戸時代の身分制度や農民の暮らしについて扱っていたときのことです。
ある生徒が問題プリントに「水呑み百姓」と書こうとして――なんと「みずむし百姓」と書いてしまいました。教室中が爆笑。本人は「えっ!? 何がそんなにおかしいんですか?」ときょとん顔。こちらもつい笑いながら、「水呑み」と「水虫」はまったく違うでしょ!とツッコミを入れた場面でした。
けれど、こういう“間違い”こそ実は大きな学びのチャンスです。
間違いは、強烈な記憶になる
人は失敗したり笑われたりした出来事を、驚くほど鮮明に覚えているものです。
その瞬間は恥ずかしいかもしれませんが、次に同じ問題が出たとき、「あ、あのとき笑われたやつだ!」と記憶が呼び起こされる。結果的に定着率がぐんと高まります。
塾の授業でも、「なるほど〜」と納得して終わるより、「あちゃー、やっちゃった!」と笑いが起こるほうが、子どもたちの表情も明るく、記憶の残り方も強くなるんです。
水呑み百姓とは?
ここで改めて確認しましょう。「水呑み百姓」とは、江戸時代に自分の田畑を持たず、土地を借りたり小作したりして生活していた農民を指します。
「水呑み」という言葉には、「自分の力だけでは米を食べられず、水をすすって暮らすほど貧しい」という意味が込められています。
一方で、授業で飛び出した「みずむし百姓」…これはもちろん存在しません(笑)。ですが、この間違いのおかげでクラス全員が「水呑み百姓」という言葉を忘れられなくなったのは間違いありません。
笑いは学びを前に進める
hal学習塾では「自律・自重・自発」という3つの「自」を大切に指導しています。
けれどそれは決して堅苦しいものではなく、こうした日常の小さな笑いも含めて、学びを楽しむ姿勢を重視しています。
テスト勉強はときに単調でつらいものになりがちです。けれど、仲間と一緒に笑いながら乗り越えることで、知識はぐっと生きたものになります。そして「次はちゃんと覚えよう!」と自発的に動き出すきっかけになるのです。
まとめ
「みずむし百姓」と書いた生徒は、きっともう二度と間違えないでしょう。
そして、その場にいたクラスメイト全員にとっても、このエピソードは忘れられない“勉強の記憶”になったはずです。
勉強はまじめに取り組むことが大前提ですが、笑いが生まれる瞬間こそ、知識が深く刻まれるチャンス。そんな場面を、これからも大切にしていきたいと思います。