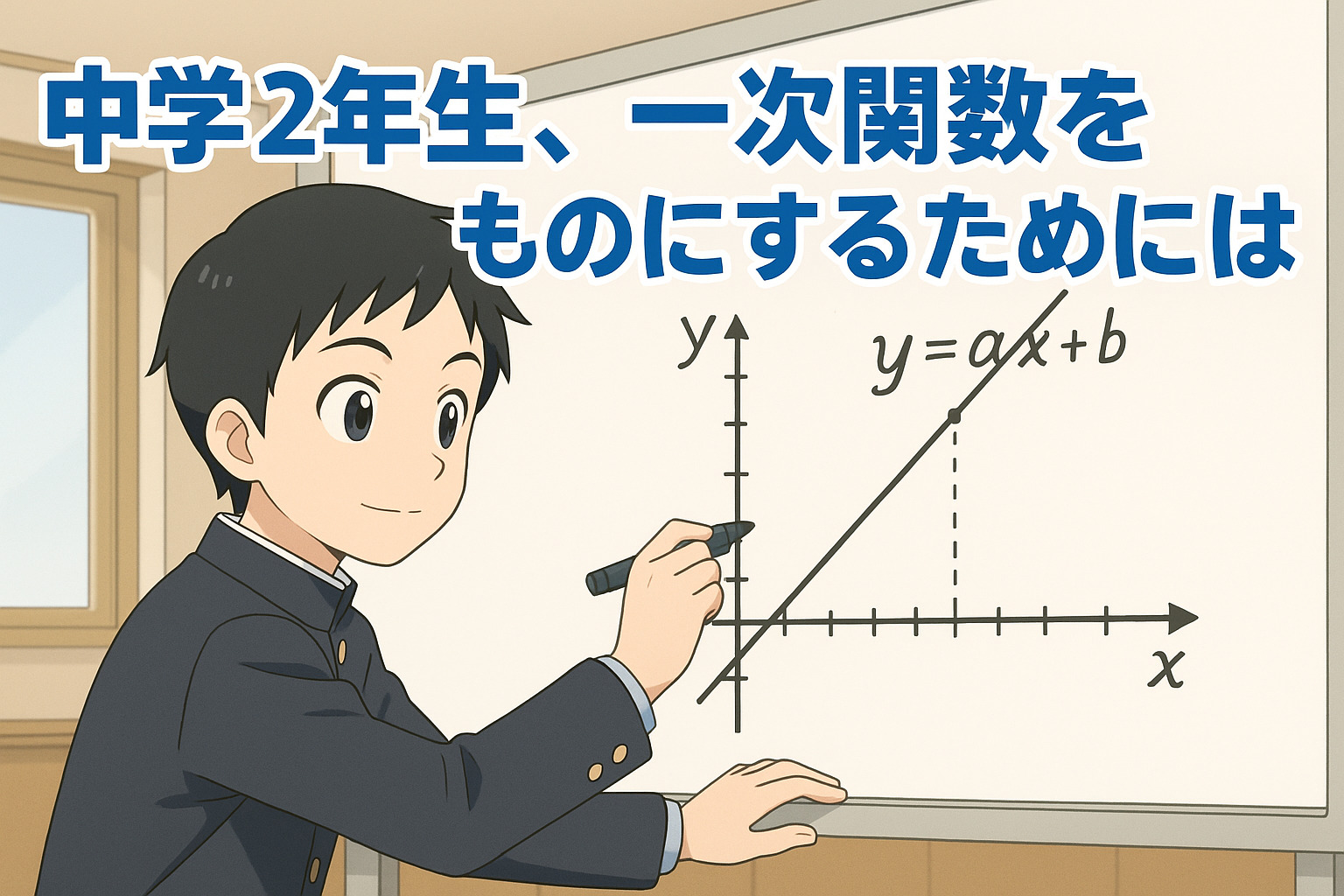中学2年生の大きな壁のひとつが「一次関数」です。
グラフや式が絡むため、苦手意識を持つ生徒が一気に増える単元でもあります。実際に、hal学習塾でも「ここでつまずいた」という声をよく聞きます。では、一次関数をしっかり自分のものにするためには、どんな勉強の仕方が必要なのでしょうか?
1. 正負の数・文字式・比例反比例の理解が基盤
一次関数は突然出てくるわけではありません。中1で学んだ「正負の数」「文字式の計算」「比例・反比例」が土台になっています。
例えば、グラフを描くときには座標を扱いますし、xの増加とyの増加の関係を理解するには、比例の感覚が欠かせません。
基礎があやふやなままでは、一次関数の理解は難しくなります。もし過去の単元に不安があるなら、復習から始めることが大切です。
2. 「y=ax+b」の意味をつかむ
一次関数の式 y=ax+b。
ここで大切なのは「a」と「b」の意味を理解することです。
- a → 傾き(xが1増えると、yはいくつ増えるか)
- b → 切片(x=0のときのyの値)
この2つをイメージできるかどうかで、グラフが“ただの作業”になるか、“理解したうえで描く”になるかが分かれます。塾では「坂道の傾き」「出発地点」といった日常のイメージと結びつけて説明することで、生徒がスッと理解できるよう工夫しています。
3. グラフを「点」ではなく「関係」として捉える
「2点を打って、直線を引いて終わり」では本当の理解にはなりません。
グラフは「xとyの関係を表している」もの。つまり、式とグラフは一体なのです。
- 式を見て「グラフの形」をイメージできる
- グラフを見て「式の特徴」を読み取れる
この“双方向の理解”が一次関数攻略のカギとなります。
4. 応用問題は「ストーリー」に注目
文章問題になると、一気に正答率が下がります。
例えば「時速と距離」「料金と利用時間」といった場面。ここでは、状況を数式に翻訳する力が問われます。
解き方の手順は以下の通りです。
- 状況を整理する(表や図にまとめる)
- 「変化する量」をxやyに置き換える
- 関係を式に直す
ストーリーを式に変換する練習を積むことが、入試問題にも直結します。
5. 在塾生の実例
入塾したての頃、一次関数の文章題はほとんど手が出なかったK君。
「速さと距離の問題?」「料金の問題? 全部ごちゃごちゃで分からない…」と投げ出しそうな状態でした。
そこで、火曜の集団授業で基礎を確認し、土曜個別で文章題を徹底練習。状況を図にして整理する習慣をつけ、「xを使って関係を表す」練習を何度も繰り返しました。
結果、2学期の実力テストでは関数の大問を丸ごと正解!「やればできる!」という自信を手に入れ、数学全体への苦手意識も薄れてきています。
このように、弱点を克服するプロセスを一緒に積み上げていくことで、確実に成長していけます。
6. 継続学習で“関数嫌い”を防ぐ
一次関数を苦手のままにすると、2次関数・三平方の定理・さらには高校数学にまで悪影響が出ます。
大切なのは「毎週少しずつでも触れ続けること」。グラフを描く練習や文章題をこなしていくうちに、「分かった!」という手応えが必ずやってきます。
hal学習塾の取り組み
hal学習塾では、中学2年生の火曜授業で一次関数にじっくり取り組んでいます。
さらに、土曜日の個別指導では復習や応用演習の時間を確保。理解が浅い子には基礎に戻り、得意な子には応用問題で力を伸ばすといった柔軟な指導を行っています。
「分かる」→「できる」→「点数につながる」まで導くことを大切にしています。
中学2年生にとって一次関数は、数学だけでなく今後の学習全体を左右する重要な単元です。
ここをしっかり乗り越えることで、受験勉強の地盤が固まり、自信も大きく膨らみます。