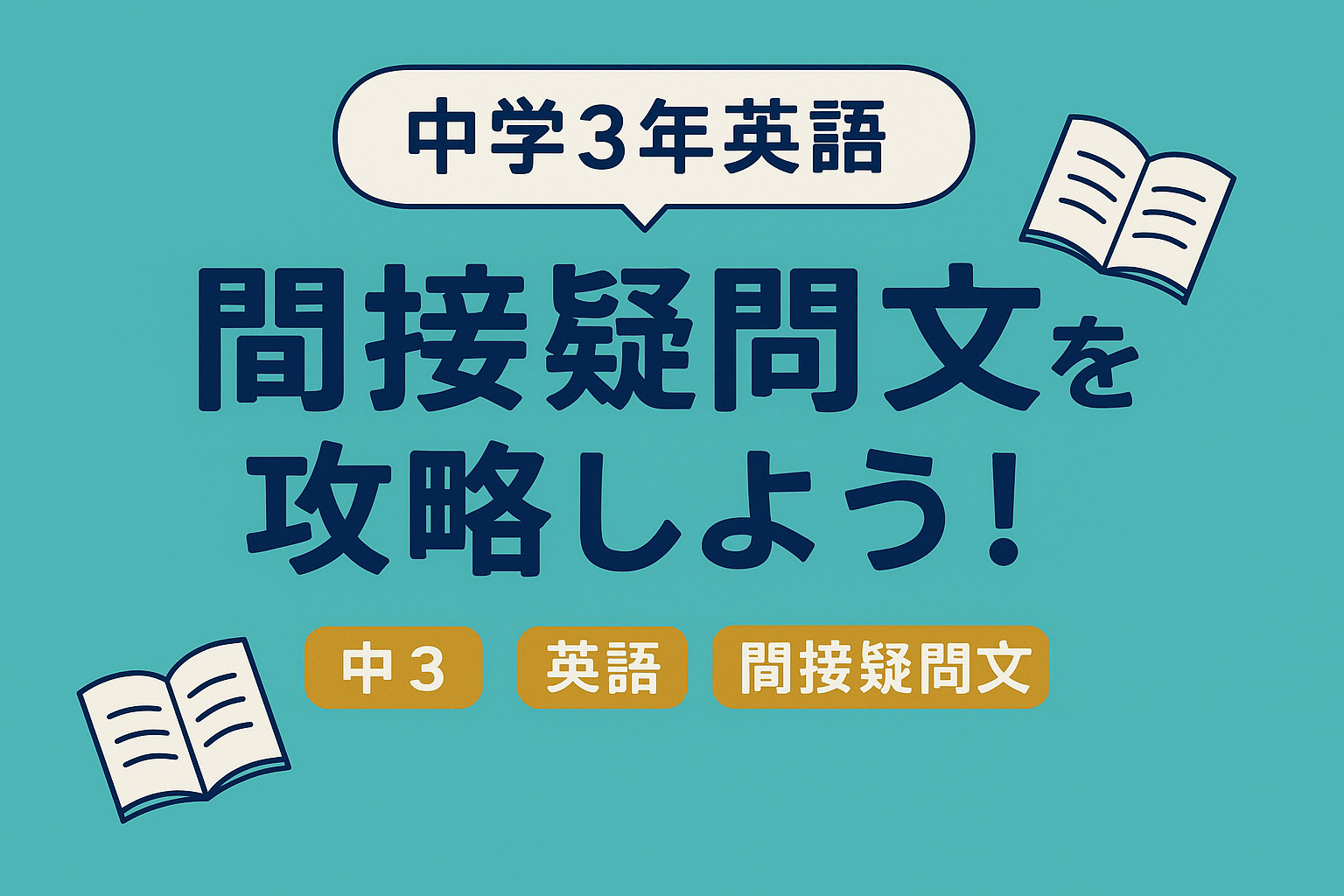中学3年生になると、英語の文法は一段と難しくなります。中2までに学んだ「現在完了」や「受け身」も重要ですが、テストや入試で特に差がつくのが間接疑問文です。
「習ったときは分かった気がするけど、テストになると迷う…」
「疑問詞を使うのに、語順がごちゃごちゃになってしまう…」
そんな声をよく聞きます。今回は、間接疑問文のつまずきやすいポイントを整理し、得点につなげるための勉強法を紹介します。
そもそも間接疑問文って何?
間接疑問文とは、疑問文をそのまま尋ねるのではなく、疑問詞を文の途中に埋め込む形の表現です。
たとえば、
- 直接疑問文:Where does he live?(彼はどこに住んでいますか?)
- 間接疑問文:Do you know where he lives?(彼がどこに住んでいるか知っていますか?)
大事なのは、間接疑問文では語順が肯定文になるというルールです。
つまずきやすいポイント
① 疑問詞がある場合
- × Do you know where does he live?
- ○ Do you know where he lives?
疑問詞がつくと、つい「does」を入れてしまう生徒が多いですが、間接疑問文では不要。
を使います。
② 時制の一致
- He asked me, “Where do you live?”
- He asked me where I lived.
過去の発言を間接疑問文にするときは、時制が一段下がることも忘れずに。
効率的な勉強法
- 直接疑問文を書き出す
まず普通の疑問文を確認。 - 肯定文の形に戻す
間接疑問文にする前に、一度「答えの文」をイメージする。- Where does he live? → He lives in Sendai.
- Do you know ~? をつけて練習
Do you know where he lives? のように、自分で作り変えて声に出して読む。
テスト対策のポイント
- 空欄補充では「does / do / did」をつけてしまうミスが頻出。必ず「肯定文の語順!」と確認。
- 長文読解でも間接疑問文はよく出る。“I don’t know why…” のような表現を見かけたら、疑問文ではなく「~なのか分からない」という意味だとすぐに気づけるように。
hal学習塾での指導例
授業ではまずホワイトボードに直接疑問文と間接疑問文を並べて書き、違いを「見える化」します。さらに、実際に口に出して読ませ、自然な英語のリズムで覚えさせます。
また、テスト前には「間接疑問文だけの小テスト」を実施。短時間で繰り返すことで、「語順を直感的に思い出せる」ようにしています。
「わかっているのにテストで間違える」というのは、理解不足ではなく練習不足。だからこそ、何度も声に出して、手で書いて、体に染み込ませることが大切です。
まとめ
- 間接疑問文は 疑問詞+肯定文の語順 が鉄則
- 時制の一致もテストでは狙われやすい
中学3年の英語は入試につながる重要単元のオンパレード。その中でも間接疑問文は、基礎を固めれば必ず得点源になります。
自分一人では整理が難しいと感じたら、ぜひhal学習塾で一緒に練習しましょう。