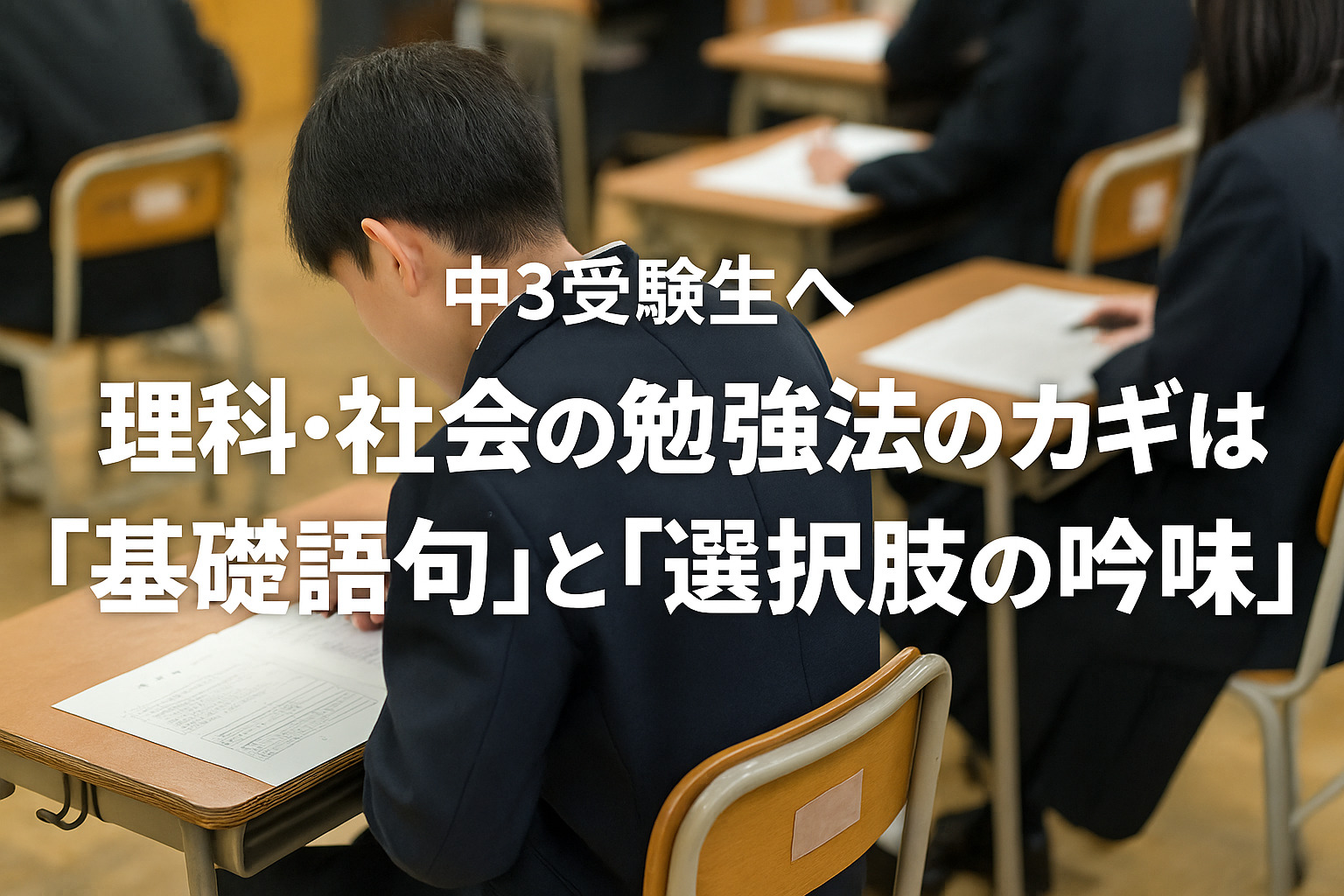中学3年生にとって、いよいよ受験勉強が本格化する時期。特に理科と社会は「暗記科目だから過去問を繰り返せばいい」と考える生徒も少なくありません。
しかし実際は、ただ過去問や記述問題を解くだけでは点数は伸びません。
合格に近づくためには「基礎語句」と「選択肢の扱い方」を徹底することが重要です。
まずは「基礎語句」を徹底的に固める
理科や社会で点数を伸ばすうえで欠かせないのは、まず基本用語の理解です。
たとえば理科なら「融点」「光合成」「電圧」「地層」など、社会なら「政党政治」「産業革命」「鎖国」「南蛮貿易」といった言葉。
この段階を飛ばしていきなり入試問題に取り組んでも、「なんとなく」で選んで間違えるだけ。
模試や入試の問題は、基礎語句を知っている前提で組み立てられています。
実際、昨年の卒塾生Aくんも、入塾当初は社会の模試で30点台。
しかし毎回授業後に「今日のキーワード10個」を覚えるよう徹底した結果、冬には70点台までアップ。
「まず語句から」――この基本を守るだけで、成績は確実に変わるのです。
模試や過去問は「選択問題」を重点的に攻略せよ
模試や入試過去問を解くとき、多くの生徒は記述問題にばかり力を入れます。もちろんそれも大切ですが、実は合否を分けるのは「選択問題」です。
理由はシンプル。入試全体の点数に占める割合が高いからです。
選択肢問題を落とさないことが、合格点に届くかどうかを大きく左右します。
そして大事なのは「不正解の選択肢」に目を向けること。
問題を解いたら「なぜこの選択肢は誤りなのか」「この用語はどんな事柄に関係しているのか」を一つひとつ確認するのです。
例えばBさん(卒塾生)は、理科で「フレミングの左手の法則」と「右ねじ(右手)の法則」をよく混同していました。右手でフレミング、左手で右ねじみたいな感じで(笑)
授業で「間違えた選択肢の内容を調べ直す」習慣をつけた結果、模試の電流分野は安定して得点源に。
「答えを出すだけで終わらない」姿勢が、確かな得点力につながった好例です。
「直し」で本当の学力がつく
模試や過去問を解きっぱなしにしてはいけません。
解いた後にどれだけ「直し」をするかで、学力の定着度は大きく変わります。
特に社会や理科は、一問間違えると関連分野をまとめて復習するチャンス。
誤答の原因が「語句を覚えていなかった」のか「似た用語と混同した」のかを分析しましょう。
Cさん(卒塾生)は模試直しを徹底した生徒。
最初は「地層の堆積順序」でよく間違えていましたが、解説だけでなく教科書・ワークに戻って確認。
直しノートをつくるようになってから、理科は40点台から80点台まで伸びました。
入試で勝つための3つのポイント
- 基礎語句の徹底暗記
土台がなければ応用はできない。まずは用語を覚えることから。 - 選択肢を吟味する練習
正解を探すだけでなく、不正解の選択肢が指す事柄も確認する。 - 模試・過去問の直しを徹底する
間違えた問題こそ伸びしろ。解き直しが本当の勉強。
受験勉強は「やった時間の長さ」ではなく「勉強の質」で差がつきます。
理科・社会の勉強を「基礎語句」と「選択肢」に重点を置いて取り組むことで、得点力は確実に上がっていきます。