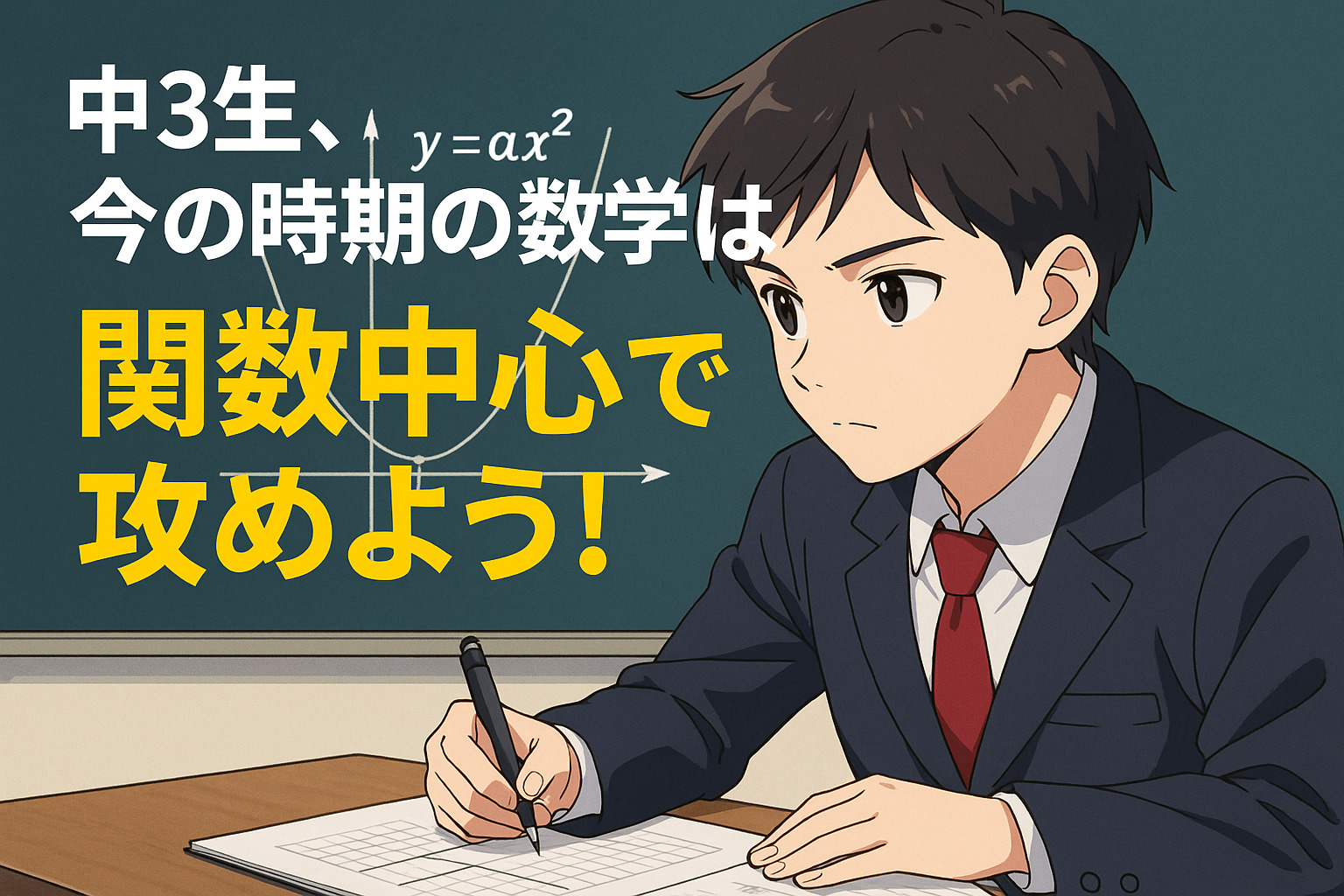10月も半ば。受験生にとってはいよいよ本格的なラストスパートに入る時期です。
「そろそろ入試問題にも挑戦していきたい!」という声も聞かれるころですが、数学について言えば、この時期はまだ“関数中心”で十分です。
なぜかというと、今の段階ではまだ相似や三平方の定理といった重要単元を学校で習っていないからです。
これらの知識がない状態で図形の入試問題を解こうとすると、かなり効率が悪いんです。
三平方の定理・相似がカギを握る理由
入試問題の図形分野では、必ずといっていいほど「相似」や「三平方の定理」が登場します。
たとえば、ある三角形の高さを求める問題でも、相似を使えば一瞬で比を立てて求められるところを、今の知識だけだと遠回りして面積比を考えたり、式を2つ立てて連立させたり…。
つまり、「分かっているのに時間がかかる」「手順がやたら多い」という状態になってしまいます。
受験勉強では“効率”も大事なポイント。
今の段階で無理に図形の入試問題に手を出すより、関数の総復習や応用練習に力を入れた方が、ずっと効果的なんです。
今やるべきは「関数の型」をマスターすること
中3の秋に重点を置くべきは、一次関数・二次関数・比例反比例の融合問題。
「グラフの交点を求める」
「2つの関数の面積比を求める」
「動点が移動してできる図形」
といった典型問題を、確実に解けるようにしておくことです。
ここを仕上げておくと、冬以降に図形や相似、三平方が加わったときに、問題の見通しが一気に良くなります。
関数と図形は受験数学の“二大柱”。
今のうちに関数の土台をしっかり固めておけば、後々の伸びがまるで違います。
「先取りより、積み上げ」を意識して
この時期、「入試問題を早めに始めたほうがいいですか?」という質問をよく受けます。
もちろん入試問題に触れること自体は悪くありませんが、焦って先取りするより、確実な積み上げを。
基礎が固まっていないまま進むと、「解けない→焦る→雑になる→ミスが増える」という悪循環に陥ってしまいます。
むしろ、今は「自分の得意パターンを増やす時期」と考えましょう。
一次関数、二次関数、連立方程式、確率、相対度数・四分位範囲など、入試で頻出の基本構成を一つひとつ完璧にしていく。
その積み重ねが、冬の模試で大きな差になります。
hal学習塾では、今の時期に合わせた受験対策を実施中
hal学習塾の中3クラスでは、10月・11月の授業で「関数の総復習+実戦応用」を徹底的に行っています。
生徒一人ひとりの「苦手関数」を見抜き、個別プリントで克服練習。
同時に、12月以降の図形単元にスムーズに接続できるよう、比例関係・座標・長さ比などの前提スキルも整理しています。
焦らず、しかし確実に。
それが受験数学を制する近道です。